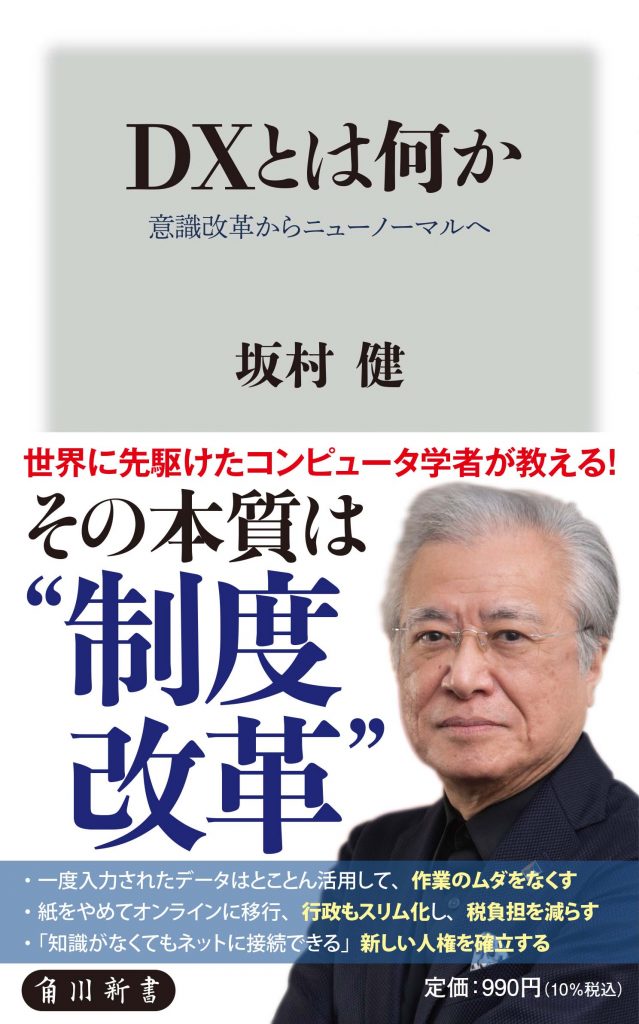坂村健氏が斬る、失敗するDXと成功するDXを分けるもの-ゼロリスク信仰を盾にデジタル化を拒む日本は変われる

ハイテク企業の代表格であるGAFAM。その躍進が勢いづき始めた頃から、世界中のあらゆる産業やビジネスにおいてDX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が広く認識されるようになった。大きく乗り遅れた日本もデジタル庁を創設するなど、国を挙げてDXの動きに追いつこうとしている。
だが、DXを成功させるためには、単なる「情報化」や「デジタル化」とは全く異なる哲学を持って、働き方そのものを全体のネットワークを考えながら組み立て直す必要がある、という。
本当のDXとは何か、どうしたら様々な単位の労働や生活の現場でDXが達成されるのか──。坂村健氏(東京大学名誉教授、INIAD<東洋大学情報連携学部>学部長)は時代に合わせてコンピュータやIoTのグローバルスタンダードを唱え、ユーザー側の考え方をアップデートし続けてきた。『DXとは何か 意識改革からニューノーマルへ』 (角川新書)を上梓した坂村氏に話を聞いた。(聞き手:長野光 シード・プランニング研究員)
──会社や行政機関などの大組織では、様々な部署が継ぎ接ぎのごとく小さなデジタル化を進めているため、ネット環境を生かした画期的な新サービスを導入しようとしても、複雑怪奇に絡み合った古いシステムが足を引っ張りあうという問題が起きています。
坂村健氏(以下、坂村):今回のコロナ禍で、行政組織が迅速に対応できないという現状があぶり出されました。
古いシステムというのは、平時においてルーティンですべてが進む状況に対応しているだけで、少しでも違ったことしようとした途端に問題が起こります。コンピュータプログラムで言えば、一箇所を変えるために、関連する何箇所にも及ぶコード(行政なら関連法規)を見直さなければならない。それに対応しても、今度は別のところが破綻してしまう。その繰り返しで問題が悪化していきます。
コロナ禍のような有事においては、それに対応するスピードが人の生死を分けることがあります。保健所の報告をずっとFAXでやっていたとか、自治体ごとにシステムがバラバラでデータの連携ができないとか、急いで何かしようと思ってもできないことの連続になる。そういうシステムを「スパゲッティ状態」と言います。
この絡み合った状況を解消するためには、結局、すべての業務プロセスを見直して、問題点の棚卸しから始めるしかないでしょう。そこで重要なのが「統一的ID」です。特に行政を含むサービス系の業務においては、サービス対象である顧客ID、つまり顧客を特定するための番号が大事です。さらにサービスする側の担当者も、自分の個人ID でシステムに入ることが大切です。
誰がどのように、データに対して何をしたのかのログ、つまり記録を取ることはセキュリティという面でもプライバシー保護という面でも重要です。日本の組織でよくあるように、個人を特定せずに総務部第2課とか住民票受付部署のような「組織ID」で業務をこなしていてはそれができません。
まずはマイナンバーの利用目的の限定列挙の解除が必要です。その上で、行政システムは少なくとも国が基本機能をSaaS(Software as a Service)のようなクラウドサービスの機能として用意し、それを自治体が条例など地方の事情に合うように調整して利用するやり方に変えるべきです。
コロナで露呈した行政手続きの前時代性
坂村:そもそも地方行政は、同じ法的な根拠に従っているのでパラメーターレベルの調整で十分できるはずです。しかし、地方自治法に定められた予算などの決まりを全部見直さなければならないために、システム開発以外の問題で何年もかかってしまう。それが今の日本の状況です。そして、そこまでやったとしても、今のやり方を電子化して開発を効率化したに過ぎない。
今の日本の行政のやり方は、「紙・ハンコ・郵送」という物理メディアが事務の大前提だった時代に確立したものです。クラウドに接続して、日本の北の端と南の端で同じデータにアクセスして互いに書き換えられる現代の事情に合っていません。
目的は同じでも、やり方まで法律化しているために簡単に変更できないのが我が国最大の問題です。技術の進歩は早いので、今後も目的が同じだとしてもその時点での最適なやり方はどんどん変わっていくでしょう。目的とやり方を切り離して、目的さえ達成できれば多様なやり方を選択できるような法律にする必要があります。
もし問題が生じたら法廷で事後審査する英米法のように対応すればいいですが、それには相当時間がかかりますし、ゼロリスクを求める国民性と反するので多くの抵抗が出るでしょう。
しかし今回のコロナ禍で分かったのは、戦争でなくても緊急の有事の可能性があるということです。緊急事態での法的な柔軟性について議論すべき時に来ていると強く思います。
──本書には、フランス・リールのスーパーマーケットが事例として登場します。このスーパーの取り組みは、生活や仕事をDXしていく上でなぜ参考になるのでしょうか。
坂村:リールのスーパー省力化を徹底しています。最も省力化に貢献しているのは、客に入力を任せるセルフレジです。
日本のセルフレジのように、重量差とスキャンした結果を突き合わせるなど複雑な不正発見の機構がないので1台あたり数万円でできる。商品ラベルのバーコードスキャンや個数の入力、割引シールの有無を客自身がして、客に店の運営に参加してもらうのがこのスーパーの基本コンセプトです。その運営協力分を価格に反映することによって商品が割安になり、さらに客が集まるという仕組みです。
日本のDX推進の最大の障壁
坂村:ところが、日本でこういう話をすると、インチキをするやつがいるから成り立たないと言われます。ただ、フランスより日本の方がミスや不正が多いとも思えませんし、実際にフランスでの不正な入力は0.5%程度です。この中には、ごまかしだけではなく間違いが含まれているでしょう。この数字は、売れ残りや傷など自然損失より小さいので無視しても構わない。
最初に銀行カードとメールアドレスを登録し、個人が特定されているのも不正に対する抑止力になっていると思います。そして、ここまで店が客を信用すると、客としては褒められた気になって裏切らないそうです。
ゼロリスクを求めることは日本のDX推進の最大の障害です。システムを設計する時にゼロリスクを追求しすぎると、コストや手間がかかって成り立たなくなる。
目的はゼロリスクでないはずなのに、いつの間にかそれが最重要課題になってしまう。皆がゼロリスクを過度に追求すると唯一の落としどころが「今まで通り」しかなくなってしまうし、そういう組織は「今まで通り」が通用しなくなると脆い。コロナ禍があぶり出したのは、まさにそういう日本の行政や企業の体質です。DXを進めるならコストとベネフィット、リスクとメリットなどのバランスを考える姿勢が重要です。
──オープンデータ、オープンソース、オープンイノベーション、オープンアーキテクチャと本書の中で様々な「オープンの哲学」やその概念を説明しています。この点を強調されるということは、それだけ日本の技術の開発の現場が「オープンの哲学」から程遠いということでしょうか。
坂村:日本ではギャランティ型(誰かが責任を持ってくれて、お金さえ払えば保証してくれるシステム)を求める傾向が強く、新しいことをやる時にベストエフォート型(皆で問題がないように最大限の努力することで成り立つシステム)でいこう、と割り切ることができません。オープンでは自分の管理下にすべてを置けないので、ギャランティ型の思考からすると不安でしょうがない。
長期の信用関係や契約関係ではない、または系列・グループ企業でない相手とネットを使って素早く連携して進めるのが今のオープンイノベーションです。世界は、ネットで問い合わせたらすぐに地球の裏側から見積もりが届くというような速度感で進んでいます。そんな時に、「見積もりの前にお会いしてお話を」というような信頼関係の構築を優先する日本のプロトコル(手順)では全くついていけません。
ソフトウェアはどこまでオープンになるか?
──今後、様々な産業やセクターでデータを公開共有してお互いに活用していくとした場合、プライバシーに配慮した形にする必要があります。このように様々なデータを公開可能な形に加工するデータ・クレンジング(データをきれいにする処理)についても説明しています。
坂村:AIの活用によってデータ・クレンジングを的確に行うことは可能です。データ・クレンジングにおいて、プライバシーの問題というのはほんの一部で、むしろ簡単な部類の問題でしょう。
同じ項目なのに年によって計測時間が違うとか、累計数と最大数が混ざっているとか、整合性がないデータを揃えるのがむしろデータ・クレンジングの難しい部分なんですね。ここでも問題はゼロリスク信仰にあります。
AIも完全ではありませんから失敗はありますが、体調やメンタル面に左右される人間よりもはるかにAIの方が安定して結果が出せるのではないでしょうか。それでも今まで通り人間ならよくてAI は怖いと考えるのは不合理です。反ワクチン運動などもそうですが、新しいことをやる際に生じるトラブルを重く考える傾向が、特に日本にはあります。課題は受け止める社会の側の反発だと思います。
──本書の「クローズへの流れ」では、コンピュータが普及し始めた頃、技術はとてもオープンな文化だったが、やがてハードウェアとソフトウェアが分かれて販売されるようになり、コピー禁止のために著作権が重視されるようになる。その後、次第に再びGitHubなどを使ったオープンな開発文化へと移り、オープンなソフトを手直ししていく「アジャイル」へと変化してきたという歴史について解説しています。今後もアジャイルからまた別の何か、例えば再びクローズな開発へ変化していくこともあり得るのでしょうか。
坂村:クローズへの揺り戻しはないと思います。なぜなら、現状でもクローズドになっている部分はあるからです。例えば、Googleの「ナレッジグラフ」(グラフ型で保持されているデータベース)のように、多くの企業はオープンなAIのソースコードを利用していますが、莫大なデータで訓練した後のニューラルネットワーク自体はクローズです。
これはオープンムーブメントのGPL(General Public License)と言われているライセンスが想定していない事態です。ニューラルネットワークにおいては、ソースコードよりもパラメーターが重要ですが、これにはGPLというこのライセンス規定の網がかからないからです。今後のオープンとクローズのせめぎ合いは、この規定外の部分をどこまでオープンにしていくかになっていくでしょう。
開発も「アジャイル」から揺り戻すことはないと思います。今、開発でアジャイル方式がクローズアップされていると言っても、銀行の勘定系のようなシステムはいまだにウォーターフォール型(確認まで終えてから次の工程に移る形式)で開発されていますし、それは今後も変わらないでしょう。
逆に、AIを使ったシステムは、本質的に詳細な仕様設計は不可能なので、どうしてもアジャイル的設計で、さらには運用しながら開発者と連携して日々改善するような方式(DevOps型)になるのは必然です。つまり、応用と技術に応じて開発方式が多様化するという流れなので、これが揺り戻すことは考えられません。
「DXを買ってこい」という経営者は退場
──「企業のオープン戦略で重要なのは、流れのイニシアチブを取るためにオープンにすべき部分と、絞り込んでここの優位性さえ確保できれば他はオープンにできるというコア資源の見極めに他ならない」「日本企業はこの部分の見極めが下手」「経営層でないと判断できない重い問題なのに情報関係ならシステム部だろう、などと他人任せにする」と書かれています。これはつまり組織の中で決定権を持つ人間にこそ知識や理解がないと、特に大きな規模のDXやオープン戦略は実行できないということでしょうか。
坂村:その通りです。細かい知識は必要ありませんが、今のネット時代の勘所を理解しない人が意思決定層を占めている組織は危険です。「DXを買ってこい」と言うようなネット自体の勘所が分からない経営層は、退陣して若い世代に席を譲るべきです。決して年齢だけで決まるものではありませんが、統計的な真実として若い人の方がイノベーション向きなので世代交代がやはり重要だと思います。
──「インターネットの責任者を呼べ」と言っても誰なのか分からない。それがオープンの負の側面と書かれています。DXが進むほどシステムやネットワークがデジタル上でより複雑に絡み合う世界になっていくと想像しますが、その中でテクノロジーに弱い人から迷子になって途方に暮れていく未来にはならないでしょうか。
坂村:個人がデジタルの知識を身につけて、自分で積極的に問題を解決していく力をつけることは社会の構成員としての義務です。その大前提を、まず社会全体で共有しなければなりません。
テクノロジーに弱い人から迷子になって途方に暮れる社会は避けられないでしょうが、どうしてもそれができない人をどう救うかは福祉と人権の問題です。ついていけない人はいるからDXをやめようというのは本末転倒です。ついていけない人がいるからDXをやめて、結果として日本全体がダメになれば、ついていけない人を助けることもできなくなるのですから。
──新設のデジタル庁についてどのような期待感を持っていますか。デジタル庁が日本に真のDXを導入するためには、どのようなことに力を注ぐべきだと考えますか。
坂村:強い危機感を持つことがキーワードになります。DXで重要なのは、局所最適ではなくて全体最適を目指すことですから司令塔が必要です。各省庁や自治体が予算を持って部分的な権限で、バラバラにデジタル化を目指す従来型のやり方ではうまくいかない。デジタル庁には是非その司令塔になってもらいたいですね。
その際、きちんと世代交代ができるかどうかが問題です。本当はトップの政治家が、「自分はよく分からないけど責任は取るから思い通りにやれ!」と言って若手を集めるとか、映画『シン・ゴジラ』の「巨大不明生物特設災害対策本部」のようなノリを期待したいですが、デジタル庁に従来型の古い権威者がいまだに多く残っているようでは不安です。2000年に当時のIT戦略会議が唱えた「e-Japan構想」に関わっていたような世代の人は関わらない方がいいです。
エストニアの行政システムを導入しようとしている市川市
──千葉県市川市は、エストニアの行政システムをそのまま導入しようという動きを見せています。地方自治体が先んじて独自にDXを図って成果を出すことで、国が真似をするという形で日本の行政のDXが達成されていく可能性はありますか。
坂村:今のままでは難しいですね。エストニアの行政システムを導入すると言っても、それにマイナンバーを使おうとしたら違法になります。単なる技術導入なら小さく始めて、もしうまくいったら全体に適用しようというのもいいですが、制度はそうはいきません。
国家戦略特区は地域限定で規制が撤廃できる枠組みです。特に「スーパーシティ」構想、これは技術に合わせて関連法規をまとめて変えられるようにするもので、大変画期的です。例えばマイナンバーを行政システムで多様に利用できるようにする改革もできます。ただそれでも住民合意が必要だという高い壁はあります。
トヨタのWoven City(ウーブン・シティ)のように、何もないグリーンフィールドから始めるというスマートシティの作り方ならできますが、市川市のように住民が既に住んでいるブラウンフィールドでどこまでできるかは、市長のリーダーシップと市民の危機感がカギを握ることになるでしょう。
──エストニアを始めスウェーデン、オランダ、ノルウェー、デンマーク、フィンランドなどDXが進んでいると言われる国は、いずれも日本よりもずっと人口の少ない国々です。中国のように国策で強引に国の政策が決められる国はさておき、民主主義国家ではサイズが大きくなるほど機動力が小さくなりDXには不利なのかもしれないと思うのですが、いかがでしょうか。
坂村:その通りです。図体が大きいほどしがらみが増えて、しがらみが大きくなるほど変わるのが難しくなります。全体最適の話と逆になってしまいますが、徹底的な地方自治というものも一つの解かもしれません。徹底的な地方自治と小さな政府思考がイノベーションを可能にしているとも言えます。ただアメリカでもNIST(国家標準技術局)のように、技術の世界では、国全体で標準化すべきことについてはきちんと司令塔があります。
また、徹底的な地方自治をやっても、今の日本のサイズでは中途半端です。地方政府の人材不足を中央が補うような構造からしても、それをやれば破綻するでしょう。しかし日本では決まってしまえば皆が従いますから、このコロナ禍で抱いた危機感をバネにして司令塔が適切に働けば、決められない、変われないという今の状況を乗り越えることができるのではないかと期待しています。(構成:添田愛沙)